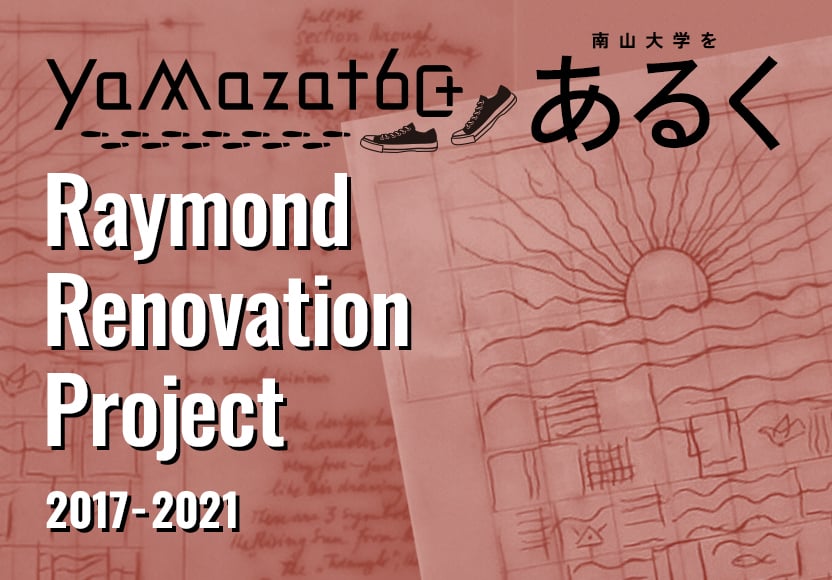南山大学の「ここ」を未来に届ける
『南山大学をはなす』
職員座談会 vol.2前編
財務課 笠井 栞さん
入試広報・高大連携課 中野 宏紀さん
キャリア支援課 池 由起子さん
情報センター事務室 岡 涼太さん
職員座談会 vol.2前編
「職員の人生もクロスするキャンパス」
『YAMAZATO60+』職員座談会の第2弾は、財務課、入試広報・高大連携課、キャリア支援課、情報センター事務室より、それぞれのプロフェッショナルに集まっていただきました。
聞き手
コピーライター 村田真美
(株式会社mana)91B154
取材日
2025年9月19日
利他の心溢れるプロフェッショナルたち
今回お集まりいただいた4名の皆さんは、「財務」「入試広報」「キャリア支援」「情報センター」がキーワードですね。「情報センター事務室」の岡さんより自己紹介と現在のお仕事についてお聞かせいただけますか。
岡
情報センター事務室の岡です。普段はS棟3階にいます。2022年に新卒で入職し今年で4年目になります。文系学部卒の私は「情報センターに配属」と言われて「ITの専門知識ないけど大丈夫?」と内心ヒヤヒヤしながらの社会人スタートでした。情報センターの主な仕事内容は、組織内のITインフラ・情報機器の整備や、システムの管理・運用と多岐にわたります。中でも私は入試システムの運用と、そのシステムを使った各種データ処理を担当しています。

「システムの運用」といいますと?
岡
利用者が不便なくシステムを使い続けられる状態を維持し、不具合や問題が起きた際には、システム開発業者と連携して原因の特定・復旧作業などを適切に対応する、というのが主な業務になります。
印象に残っている仕事でのエピソードなどありますか?
岡
忘れもしない入職1年目の失敗談です。入試後、合格通知書を何千枚と膨大な枚数を印刷するのですが、私が設定を間違えて指定とは違う書体で印刷してしまったんです。それに気づいた時にはすでに7割ほど印刷が終わっていました。出力後は入試課(現:入学センター)による確認や発送作業があるので、後工程の方々が待ち構えています。課室全体で青ざめながら、再印刷。印刷が終わるまでの間、滝汗が止まりませんでした。
それは大変でしたね。聞いている私にもその緊張感が伝わってきました。情報系の専門知識なく情報センターにいきなり配属、ということですが、大丈夫でしたか?
岡
それが、やってみたら結構面白くて。勉強した知識がすぐ仕事に生かせるし、業務効率改善のために自分で簡単なシステムを作ったりできるので、「仕事が楽しい」という気持ちの方が大きくなり、最近は「ここに配属されて良かった」と思っています。
さすがです、岡さんの適性を見抜いた配置だったのかもしれませんね。
岡
サッカーと麻雀に明け暮れた学生時代からは、想像もつかない未来が拓けました(笑)。
ご出身はどちらですか。
岡
福岡の出身で、関西の大学に通っていたのですが、妻の地元が名古屋だったのでこの地区で大学職員をやりたいな、と徐々に東へと移ってきました。
続いて池さん、お願いします。
池
2022年の10月に入職して、キャリア支援課に配属されました。転職組で、中野さんとは同期になります。キャリア支援課での仕事は主に就活生のサポートで、学生向けのガイダンスや講座などの運営や、学生のエントリーシートへのアドバイスなど学生の個別相談にのったりしています。就職内定が決まった学生が報告に来てくれたり、なかにはお礼の手紙をくれることもあるんですよ。頑張る学生たちの支援にやりがいを感じながら仕事をしています。

もともと学生支援をしたい、という思いがあったのでしょうか。
池
前職は金融関係で全く畑違いの転職なのですが、もともと教育関係に興味があったんです。教育関係の仕事をいろいろ探していたところ、大学職員に目が留まりました。学生と関われる、直接支援する仕事がしたい、と志望して運よく現在のキャリア支援課への配属が叶いました。
学生から就活の相談を受けるなかで、南山っぽいと感じることはありますか?
池
謙虚なんですよ、学生たち。就活は自分をアピールする場ですが、なぜか南山の学生は控えめというか。例えば「私なんか」とか、「これが苦手なんですけど…」と「ありのままの自分を話す」という感じで、すごく性格がいいんです。就活はアピールの場だから、ネガティブなことは聞かれたら答える程度にして、まずは「自分のいいところを言語化して伝えよう」とアドバイスを贈るようにしています。
「学生が謙虚」という言葉はこれまでの座談会でも耳にしたような…
池
学生の話を深堀りして聞いていくと、実は「強み」といえるネタの宝庫なんです。それに気づいてからは、学生が自身の個性に気づいて「強み」として言語化できるようなサポートを心がけるようになりました。
‘勇気づけ’の池さんですね。さすがです。
池
でも入職1年目の頃は、「まだ内定先が1つもなくて」と泣きながらキャリア支援課へやってくる学生の話を聞いたあとで、私も泣いてしまうことがありました。学生の不安な気持ちが自身の学生時代の就活と重なってもらい泣き。「そうだよね、友だちには言いづらいし、心配かけちゃうから親にも言えないよね」と私も辛くなっていたんですが、「これではいけない」と思い、なるべくポジティブな気持ちになってキャリア支援課から送りだそう、と気持ちを切り替えるようになりました。
南山キャリア支援課の基本方針は「大学生活を通じて自立した社会人に成長させること」です。すべてお膳立てをして「就職させてあげる」というよりは、学生自身が気づき行動を起こせるようなヒントを示すようにしています。就活も「成長の機会」として、社会へ羽ばたいていって欲しいと願います。キャリア支援課はQ棟の2階にあるのですが、初めて来る学生などは緊張した面持ちで入ってくるので、話をした後にはまた来たいな、と思ってもらえるよう笑顔を心がけています。
続いて中野さん、お願します。
中野
入試広報・高大連携課の中野です。2023年の4月に入職、池さんと同期です。前職は百貨店で、催事や人事の仕事を経験しました。南山での最初の2年間は入試の運営を担当していて、先ほどの岡さんのエピソードにあったように、合格通知出力後の確認作業にも携わっていました。今年の4月からは入試広報を担当しており、現在の仕事内容は7月に開催したオープンキャンパスの運営や、大学案内誌の制作などです。入試の運営も広報の運営も、基本的には課室の中で準備することが多いので、私はキャリア支援課の池さんのように学生と日常的に触れ合うことがないんですよね。一日の中で、昼の休憩で外へ出た時に学生の姿を見かけるくらいです。一年かけて地道に準備をして、入試本番の日やオープンキャンパスの日を迎えるのですが、キャンパスで高校生の緊張した顔や、嬉しそうな顔、推薦入試や総合型入試などは10月11月に終わるので、試験を終えた高校生たちが「やった!」と抱き合って喜んでいたりする瞬間に立ち会ったりすると、私たちが一年かけてやってきたことがここに繋がったんだなと胸が熱くなります。とてもやりがいのある仕事だと思っています。

入試の運営は特に緊張感が漂いそうです。
中野
入試当日に向けて周到な準備をして、ミスなく漏れなくやっていく、という感じなので、準備段階から気が抜けないですよね。
現在の入試広報という立場は、前職の百貨店の催事での経験を存分に生かせそうですね。
中野
どれだけ多くの人に来ていただけるか、どれだけ魅力的にみせるか、という共通点があると思います。私は南山の総合政策学部出身なんですけど、ちょうど瀬戸キャンパスがなくなる2017年の卒業生なんです。母校に貢献したいと思い転職して、広報に携わることができて幸せです。
続いて笠井さん、お願いします。
笠井
財務課の笠井です。財務課は同窓会館という建物にあって、森の中のような雰囲気の場所にあります。2015年に新卒で入職して、最初の配属先は教務課で6年間、2021年からは現在の財務課で仕事をしています。南山に入職して10年が経ちました。教務課では毎日のように学生や保護者の方、先生方の対応をしていたのですが、現在は学生や先生方と関わることはほぼなく、ずっとパソコンの前にいます。南山大学の財源のほとんどが学納金ですから、財務課の使命は、効果的に予算配分をして、皆さんに質の高い教育・研究を提供することだと思っていますので、常に学生視点を大切にしながら仕事をしています。

財源は組織の血液ですから、滞ることなく必要なところに流していくことが重要な任務になりますよね。
笠井
そういう意味では、すべての課室に関わる仕事ですよね。
岡
情報センター事務室は、事業計画のために、各課室からの「システム化したい」という要望を取りまとめているのですが、各課室からの要件を積み上げていくと結構な金額になるんですよ。基本的に大学の予算は前年度申請で、次年度に執行するという流れなのですが、IT絡みのものは「どうしても今年度やりたい」という案件も出てくるので、いつも財務課には申し訳ないと思っています。
笠井
必要な予算ですから、岡さんが申し訳なく感じる必要はないですよ。(笑)
岡
できる限りコストカットできるように内容の精査はしていますので…
立場上、厳しくしなきゃいけないんですね。財務課に来て、性格が変わったと言われたりしますか?
笠井
私、本来は大雑把な性格なんですけど、業務上はそうは言っていられません。配属されたばかりの頃は、ちょっとした気の緩みが後に大きな影響を及ぼしてしまい、「最初に直しておけば良かった…」という失敗経験を経て、慎重になりました。私の感性に任せると、「ま、いっか」となりがちなので、「とにかく周りに相談をする」と決めています。ありがたいことに、うちの課室はとても雰囲気が良く、なんでも相談できる方ばかりなので、少しでも迷ったら相談するようにしています。

職場の雰囲気がいいという話は、いろいろなところから聞こえてくるので、どこの課室も同様なんですね。
笠井
そうですね、新卒で入職した際に配属された教務課でも、職員の方と旅行に行ったり、教員の方々と飲みに行ったりと、分け隔てなく接していただいたので、とても居心地が良かったです。
新卒で南山の大学職員を希望されたのは、何かきっかけなどあったのですか?
笠井
大学職員をしている兄から「大学が好きだったら絶対楽しいよ」という話を聞いて、魅力を感じていました。私は京都の大学に通っていたんですけど、就職先としては、地元に帰っていきたいなという思いがありました。東海圏の大学といえば、やっぱり南山だろうと。南山出身の友人がいて、キャリア支援課のサポートの話や、サークル活動に邁進している話を聞いてたので、親近感もありました。
大学が好き、という話がでましたが、笠井さんの人生において大学時代を過ごした空間、キャンパスというのは、どういう意味を持っていましたか?
笠井
高校までは授業の時間割が決まっていて、その通りに勉強をすれば卒業できますよね。大学に入ると、まず受ける授業も自分で決めなきゃいけないし、サークル活動なども自分から動かなければ、何もせずに終わってしまうという焦りがあって、始めは戸惑いました。でも自分でやろうと思えばどこまでもできるし、助けを求めれば助けてもらえる、「選択の自由」がある環境がすごくいいなと思いました。
素敵ですね。笠井さんが自分らしく過ごせた4年間だった、ということですね。
笠井
一方で、「自分から動かなければ何者にもなれない」ということを知った場でもありました。
YAMAZATO60プロジェクト、見てました?
皆さんの人となりが少し見えたところで、本題へと移っていきたいと思います。 「YAMAZATO60プロジェクト」のことはご存じでしたか?

中野
ポスターを見かけたり、フォトコンテストをやってるんだ、という感じでプロジェクトのことは知っていました。広報的な視点でWEBサイトをのぞいてみたところ、「学内のことを生の言葉で対外的に発信している」ことがすごく魅力的だと思いました。これまで本学ではあまり見られなかった取り組みだな、と。
私も、お話を聞いて興味を惹かれたことを結構そのまま記事にしてるんですけど、奥田副学長や山岸副学長から「これはちょっとNG」みたいな指摘がまったく入らなくて驚いているくらいです(笑)。キャンパスという空間に息づく人々の営みを、さまざまな視点から眺めてみる。「恣意的な物語にしない」という企画意図が体現されたプロジェクトだなと思いながら伴走しています。
中野
対外的な広報の際にも、「YAMAZATO60」シリーズはいろんなネタが転がっているので、南山を紹介する際にとても使いやすいコンテンツだと思っています。
印象に残っているコンテンツはありますか?
中野
学部長のインタビューが良かったです。それぞれの人となりを含めて、学部の特色が出ているなと思いました。私が業務で携わっている、高校生に向けて制作する大学案内誌には載っていない、学部長がかみ砕いて紡ぐストーリーに惹かれました。ポスターにもなっていましたが、ビジュアルもインパクトがありましたよね。
意外な一面を見られた、というギャップも良かったのかもしれません。このWEBサイト制作に携わるアートディレクターやカメラマン、デザイナーほかクリエイティブ陣をはじめ、何よりこの企画を牽引する奥田プロデューサーの旗振りのおかげですね。笠井さんはいかがですか?
笠井
学内ポータルのポルタからコンテンツアップのお知らせがくる度に、サイトをチラッと見ていました。最近では学食企画が面白かったです。男子学生の「やっぱりお米は多い方がいい」というコメントはリアルな声ですよね。レーモンド・リノベーション・プロジェクトの記事は、キャンパスのいろんなところに意味があることを知れました。メインストリートが人と人との距離を近くするよう設計されていることや、建物の塗装がこの土地の土の色を表していることなど、普段何気なく過ごしているキャンパスですが、意味を知ると愛着が増します。この自然豊かなキャンパスは、レーモンド氏のコンセプトを守り続けているのだと感動しました。
岡さんはいかがですか?
岡
YAMAZATO60の時は副学長対談の記事を読んだ程度だったのですが、今年度の「+(プラス)」になってからは、同じ立場の職員や教員の方々が登場しているので、皆さんがどんなことを考えてるのか、とすごく興味があって毎回楽しみに読んでいます。職員座談会の第1弾に登場した門野さんと三竹さんは同期ということもあり、より親近感を抱きながら読み進めました。あとは教員座談会の番外編、クロストークが面白かったですね。研究領域が違う先生たちのディベートに引き込まれました。
そう言っていただけてちょっと嬉しいです。研究クロストークを、頑張って番外編として独立した記事にした甲斐がありました。
岡
受験生にとっても、「大学ってどんな授業をするんだろう」、という漠然とした疑問があると思うんです。私の経験では、「イメージしていた授業内容と全然違う」なんてことも結構ありました。そういう受験生の認知のズレを埋める意味でも、研究領域が違う先生方が、ざっくばらんに語っていただくトークセッションはとても有意義だと思いました。
学部ごとに独立性が高い大学だと、学部の垣根を超えたトークセッションを企画として成り立たせるのは難しい、という話も聞きますが、南山は「文理融合」を地で行く大学なんだな、と私も思いました。
岡
あと、同じキャンパスで働く方々や学生の考えに触れると、共感することが多くて、「ここが自分の居場所だ」と実感もできますよね。
先ほど笠井さんが「大学が好き」と言っていましたが、「YAMAZATO60+」を通じて、「大学が好き」と感じる方がもっと増えるのではないでしょうか。
池さんはいかがですか。
池
私はメインストリートを歩くたびに、G棟の廊下にポスターがズラッと貼ってあるのを眺めていました。色使いもポップな感じで気分が明るくなるな、と。最初の副学長対談だったかな?そのなかで「‘山里’に焦点を当てる」という言及があり、それが印象に残っていました。キャンパスを起点に、「山里」という地名で大学をブランディングしていくのはいいなと思いながら記事を読みました。

「大学が好き」という職員の皆さんの和気あいあいトークが盛り上がってきたところで、前編はここまで。続きは後編でお楽しみください。
後編に続く