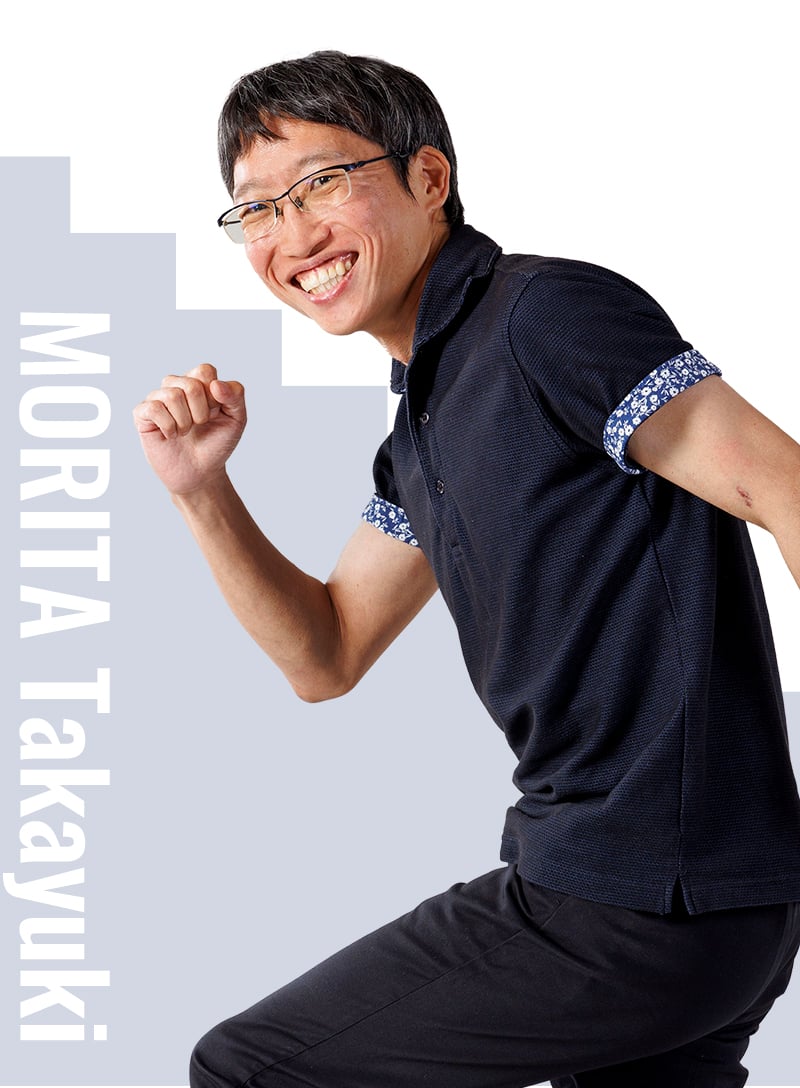南山大学の「ここ」を未来に届ける
『南山大学をはなす』
教員座談会 vol.2後編
人文学部 日本文化学科 森田 貴之さん
外国語学部 スペイン・ラテンアメリカ学科 額田 有美さん
法学部 法律学科 大原 寛史さん
教員座談会 vol.2後編
人が営む有機的な連なりを、未来へ
『YAMAZATO60+』教員座談会vol.2<前編>では、人文学部の森田先生、外国語学部の額田先生、法学部の大原先生の研究についてお聞きしました。ここからはメインテーマである、「Beautiful Campus」と「Nanzan Mind」について、そして未来に向けた話へと進めていきます。
聞き手
コピーライター 村田真美
(株式会社mana)91B154
取材日
2025年6月19日

Beautiful Campus & Nanzan Mindへの想い
本企画共通のテーマ、「あなたにとってのBeautiful Campusとは?」。お気に入りの場所や思い出の場所、キャンパスの魅力などお聞かせいただけますか。大原先生からお願いします。
大原
個人的には、それぞれの魅力的なキャンパスの場所につながる「メインストリート」を挙げたいと思います。このメインストリートがまさに「木の幹」として、各施設やそこで行われている研究・教育という「花」や「実」を育み、南山大学「山里キャンパス」の歴史を形成しているように感じられます。初めて南山大学を訪ねたとき、「山里キャンパス」のメインストリートを基盤として展開されている設計が特徴的で素敵だと思い、印象に残っていました。

正門から見たメインストリート
法学部の拠点は法科大学院棟であるA棟ですよね。山手通門からキャンパスに入ってくると、メインストリートを通らずに直接A棟に行けるので、日常の動線上ではないメインストリートを大原先生が挙げられたのは少し意外でした。
大原
初めてきた時は正門から入ったので、その時のインパクトですね。本学に着任してからは、講義、研究、業務などの合間に、メインストリートを中心に散策をしています。メインストリートを歩いていると、様々なバックグラウンドをもった教職員や学生、留学生、地域の方々がこのキャンパスに集まり、出会い、様々な表情で挨拶や会話をしながら行き交う活気に溢れた光景に触れることができます。そのたびに「ああ、もしかしたら出会わなかったかもしれない方々が、縁あって南山大学に関わり、出会い、キャンパスの各所で、そして世界の様々な場所で活躍していく…」とめくるめく妄想を繰り広げています。
このキャンパスがそれぞれの人生における「歴史」の一部となっていて、それらが集まって南山大学の「歴史」を創り出している。メインストリートは単なる「導線」ではなく、まさに南山大学の発展を願う「木の幹」の役割を担うシンボルとして創られたように感じられるのです。

キャンパス設計者のレーモンドさんの意図が伝わってきたのですね、すごいです。額田先生はいかがですか?
額田
私は「脇道」の方が好きかもしれません。授業をF棟やB棟ですることが多いのですが、そこへのアクセスは脇道経由なんです。「山里キャンパス」は小高い丘になっているので、キャンパス内も自然の地形を生かしたアップダウンがありますよね。特にF棟は少し坂を下ったところに位置するので、下層階から窓の外を眺めると、グリーンエリアがすごく綺麗に見えて、まるで森の中で授業をしている感覚になります。

H棟とG棟の間の「脇道」
奥田副学長からの受け売りですが、レーモンド建築は深いところまで自然光がちゃんと入るよう設計されているそうです。キャンパス全体が緑に包まれていますよね。特にF棟の辺りは、私の学生時代から「森の中」の印象でした。とっても気持ちがいいですよね。森田先生にとってのBeautiful Campusは?
森田
私以外、誰も通らないんじゃないかと思っている、お気に入りの通路があるんですけど。
どこですか?気になります!
森田
第1研究室棟の一番西側に私の研究室がありまして、研究室を出るとすぐに階段があり、そこを降りていくとライネルス中央図書館と直結する通路があるのですが、、、そこ、ほとんど誰も通らないんです。

図書館と第1研究室棟をつなぐ通路
確かに、あの場所は関係者しか入ってはいけない雰囲気が漂っています。
森田
その通路のおかげで、雨が降っていようと、雪が降っていようと、暑かろうが寒かろうが、図書館への移動がラクラクなんですよ。私は本当にラッキーだと思っています。雨に濡れずに、資料の持ち運びができますし、思い立ったらすぐに図書館へ行けるというのは、文学研究者にはこの上ないメリットなんですよね。
レーモンド建築のコンセプトを具現化した配置ですよね。研究者フレンドリーな設計。
森田
あの通路は、研究と教育をつなぐ架け橋だと思っています。地形の高低差を生かした設計で、まるで空中通路のようになっていて、そこを通るのが好きなんですよね。また私が授業で行くのはK棟、M棟、F棟が多いので、第1研究室棟からは雨でも傘なしで研究室と往来できて、研究と教育を繋げる設計だなと実感します。さらにもう1つ、好きなところがありまして…
盛り上がってきましたね(笑)。
森田
第1研究室棟って、メインストリート側から見ると直線的に見えるのですが、実は曲線になってる部分があるんです。私の研究室からエレベーターホールに向かって歩くと、外壁が、よーく見るとゆるやかな曲線になっていてとても美しいんですよ。

ゆるやかな曲線になっている第1研究室棟の外壁
それは知らなかったです。まだまだキャンパストリビアが眠っていますね。森田先生がこんなに情熱を込めて‘曲線’について語っていただけるとは(笑)。では次のテーマ、Nanzan Mindへと移っていきましょう。「あなたはどんなところにNanzan Mindを感じますか?」。引き続き、森田先生お願いします。
森田
やはり南山の教育モットーである「人間の尊厳のために」が、学生にも教職員にも‘自然と’浸透しているところでしょうか。根源的な、一番大事なところが皆の共通言語になっている。
額田
おっしゃる通りだと思います。私も着任3年目ですけど、本を読んでいたりして「尊厳」という言葉が出てくると、「授業で使えるかもしれない」と思わず付箋をつけてしまいます。もうひとつ、「南山生の縦のつながり」をNanzan Mindに挙げたいと思います。メキシコで知り合った、パワフルに現地で活躍されている方も南山の卒業生でしたし、「南山で教員をしている」と話すと「私も南山出身なんです」という方々にこれまで山ほど出会ってきました。教員になって、私も南山ファミリーの一員になれた気分で嬉しく思っています。
確かに、私の学生時代から「イスパニヤ科(現スペイン・ラテンアメリカ学科)」の方々って、エネルギッシュな方が多かったイメージがあります。その歴史が脈々と今に続いてるんですね。大原先生はいかがでしょう。
大原
2点あります。1点目は、先ほど森田先生がおっしゃったように、教育モットーである「人間の尊厳のために」の浸透において、です。これまで自身が関わった南山大学におけるすべての取組みにおいて、一緒に取り組んだ方々すべてが、それぞれ意見や方法などは異なっていても、教育モットーとして掲げられている「人間の尊厳のために」を実践しようとしているところにNanzan Mindを感じます。
2点目は、1点目にも関わりますが、「南山らしさ」のあくなき探求において、です。時代の変遷にともない、現在大学は様々な変革が求められています。その対応のための取組みにおいても、いわゆる「言われたとおり」の無難さや、「世間的なトレンド」という見栄えのよさにとらわれず、どうすれば「人間の尊厳のために」を実現し、それに基づく「南山らしさ」を活かすことができるかを追求し続けるところですね。それぞれの点において、Nanzan Mindがおおいに感じられるとともに、そういったNanzan Mindに、学長方針で掲げられている「地球規模の関心、私たちの貢献」や「3Ds(Dignity、Diversity、Dialogue)」が現れていると感じています。
『YAMAZATO60+』へのアイデア募集!

ここからは『YAMAZATO60+』の企画アイデアラッシュをしたいと思います。額田先生、いかがですか。
額田
ランチ企画はどうですか?南山と交流がある海外の大学所在地の名物料理を、学食で「ランチ交流ウィーク」みたいにして、国替わりで提供したら楽しそうです。
いいですね、ワールドプラザに参画している留学生たちに、それぞれ出身国の料理を披露してもらうのも良さそうですね。ありがとうございます。続いて大原先生、お願いします。
大原
学生発の企画を募集する、というのはどうでしょうか。個人的には、学生のみなさんの「アレ、もっとこうしたいよね」とか、「こんなことできたら、オモロイのにね」なんていうちょっとした気付きや思いつきを、大学が戦略的な視点や手段、サポートを加えてカタチにしていくことができたら面白いのではないか、と思っています。例えば、M-1グランプリのような、「YAMAZATO60+ 1グランプリ」みたいな?山里キャンパスの魅力や対外的知名度をさらに高め、大学全体をさらに発展させるためのキャンパス活用法や、イベント企画のアイデアなどを募り、キサラ学長、奥田副学長、山岸副学長が「これオモロイやん!」と感じたものに協力・支援をして、学生・教員・職員で大学を創り上げていくという試みも「オモロイ」のではないかと考えています。
アイデアピッチを『YAMAZATO60+』の延長線上でやるのもいいですね!SNSで配信しちゃうとか。いいですね!では森田先生はいかがでしょうか。
森田
私は「地域に愛される大学」であって欲しいという願いを込めて、大学の施設を地域の方にも使ってもらえるような取り組みはどうか、と思っています。
大切な視点ですね。地域あっての大学、また逆もしかりで、地域の誇りと思ってもらえるような大学であって欲しい。この対談企画の最初に、奥田副学長が「これからの大学は、地域の中の大学として在るべき、だからこの企画名にも『山里』という地名を冠したんだ、というお話をされていました。どうやったら地域に開けた大学になりますかね。
森田
山里町のイベントとして、地域の運動会を南山キャンパスでやってもらうとか?学食をもっと地域の方にも使ってもらうとか?
安全上の課題もあるかもしれませんが、キャンパス内を地域の親子連れが気軽に訪れる風景を描けると素敵ですよね。皆さん、それぞれのアイデアをありがとうございました。
南山らしさを後世に引き継いでいく
では最後の問いです。「20年後の南山創立100周年に向けて、どんな大学であることを期待しますか?」
森田
学生時代は、部活やバイトなど学内外含めていろいろな経験をすると思いますが、学生の皆さんには、卒業してからもキャンパスの景色を思い出して欲しいんです。キャンパスがあってその中に自分がいた、その風景を常に思い出せるような、心の拠り所であって欲しい。ビルになっている大学も多いなか、キャンパスがあるって贅沢なことだと思うんです。そのためにも活気があるキャンパスであり続けて欲しいですよね。キャンパスの景色と学生生活の思い出が結びつく大学。

20年後もその先も、キャンパスはここに在り続ける。
森田
そうですね。南山って、少しずつ建物が増えたりはしていますが、創立時の景色が残っていて、どの時代の卒業生でも自分が通っていた時代の景色を「思い出せる」キャンパスだと思うんですよ。キャンパスと共に、空間や経験、思い出とが結びついていく、そういう大学であり続けて欲しいと思います。
聞いた話では、一時期、南山もキャンパス内の建物を刷新する計画があったそうです。資金面の目途がついて、なんとか保持する方向に落ち着いたとか。その方向に舵取りした以上、20年先まで南山創建時のキャンパス構想を維持していただけることを期待したいですよね。では額田先生、お願いします。
額田
やはり南山大学の強みの一つは歴史だと思います。そして10万人を超える‘元南山大生’がいる。60年、70年、80年、100年と、脈々と続く歴史を、200年、300年と積み上げていって欲しいです。
「縦のつながり」という言葉が随所に出てきました。額田先生にとって、その価値とは?
額田
具体的に顔が浮かぶんですよ、メキシコなどラテンアメリカ各地で活躍されている魅力に溢れた人たちの顔が。海外に出ても何かの拍子に「南山」という縁でつながるんですよね。南山ネットワークが世界中にあるので、とても頼もしいと思います。このつながりが続いて欲しいし、また私たちが繋いでいかないと、と思います。

頼もしいメッセージをありがとうございます。大原先生はいかがですか?
大原
様々な場面で、時代や社会に適合することが求められています。もちろん時代やそれにともなう社会の変化に対応する必要性を否定するわけではないのですが、そのような中でも「守らなければならない」または「守るべき」重要なものがあると思います。「人間の尊厳のために」やそこから形成される「Nanzan Mind」は、その重要な一部として位置づけられる、他に類をみない「南山らしさ」だと考えています。

教職員、在学生、卒業生など関係者の方々と南山大学の話をするとき、よく「南山らしいねぇ」というフレーズが笑顔とともに出てきます。「南山らしさ」が関係者の皆様にとっていつになっても変わらずに大切なものであることのあらわれですよね。「南山らしさ」を失うことなく、時代や社会の変化に対応しながら発展していくことができる大学であって欲しいと思います。
お三方とも、ある意味共通していたのは「普遍的な南山らしさを大切に」というメッセージですね。
森田
あともう1点いいですか。古典文学などもそうですが、人間ってストーリーで教わると記憶に残るんですよ。ですから、南山のストーリーを、学生や教職員、そして地域の皆さんにも知ってもらえたら、より愛してもらえるんじゃないかと思いました。お互いがそのストーリーの中の住人になったら、もっと大事にしよう、という意識が芽生えるのではないかと。100周年を迎えるころには、そういった南山ストーリーで溢れる環境になっているといいなと思いました。

ここ「山里キャンパス」に脈々と息づく宝はすでにある。それをストーリーとして言語化していけば、未来へと語り継がれていく。このYAMAZATO60+プロジェクトシリーズは、その一翼を担っていけるかもしれませんね。今回のトークセッションはここまで。後編もお読みいただきありがとうございました!
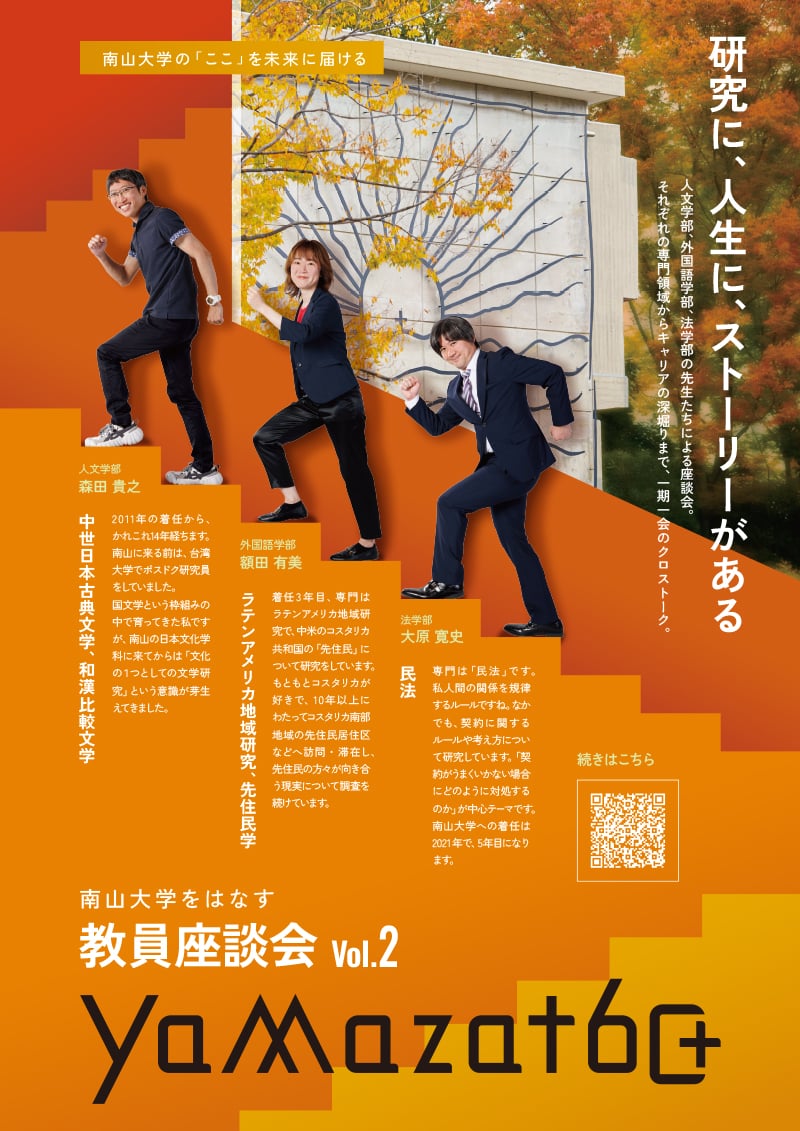
Profile
人文学部
森田 貴之 教授
専攻分野
中世日本古典文学、和漢比較文学
主要著書・論文
- 『平家物語評判書集成』(共編、汲古書院、2024)
- 『異性装 歴史の中の性の越境者たち(インターナショナル新書)』(共著、集英社インターナショナル、2023)
- 『奈良絵本『太平記』の世界―永青文庫所蔵『絵入太平記』全挿絵影印ならびに研究』(共編、勉誠社、2022)
将来的研究分野
軍記物語を中心とした中世の歴史文学の研究
担当の授業科目
「日本文学史A」「古典資料講読」「モダンの系譜―文学をめぐって2―」「中世文学研究」「日本文化学演習」「日本文化学基礎演習」
Profile
外国語学部
額田 有美 講師
専攻分野
ラテンアメリカ地域研究、先住民学、共生学
主要著書・論文
- Culture As Judicial Evidence: Expert Testimony in Latin America(共著、University of Cincinnati Press、2021)
- 『法廷において文化と向き合うーコスタリカにおける「裁判所」の民族誌ー』(単著、大阪大学COデザインセンター、2019)
将来的研究分野
フードスタディーズ、先住民学、共生学
担当の授業科目
「ラテンアメリカの文化と社会」、「民族問題と人間の尊厳」、「初級スペイン語」他
Profile
法学部
大原 寛史 准教授
専攻分野
民法
主要著書・論文
- 「ドイツにおける事実的不能の位置づけ――ドイツ民法275条2項をめぐる議論を中心に」同志社法学61巻6号65頁以下(2010年)。
- 「契約責任法の改正と履行不能――履行不能の判断基準と契約規範との関係性」加藤新太郎=太田勝造=大塚直=田髙寛貴編『加藤雅信先生古稀記念 21世紀民事法学の挑戦下巻』63-87頁(2018年)。
- 「投資取引・高齢者取引と家族の関与――『被害者側の過失』としての考慮をめぐる近時の裁判例に焦点をあてて」南山法学47巻3=4号277ー344頁(2024年)
将来的研究分野
契約法における「自律」と「他律」
担当の授業科目
債権法総論、契約法など