
南山大学の「ここ」を未来に届ける
『南山大学をはなす』
教員座談会 vol.1前編
経営学部・経営学科 余合 淳さん
理工学部・データサイエンス学科 小市 俊悟さん
社会倫理研究所 森山 花鈴さん
教員座談会 vol.1前編
フラットに、風通しのいいアカデミア
今回の座談会メンバーは、専門分野の異なる先生たち。研究者、教員という肩書きはあれどひとりの人間、南山大学という縁でつながる彼らのトークセッションをお楽しみください。
聞き手
コピーライター 村田真美
(株式会社mana)91B154
取材日
2025年6月10日
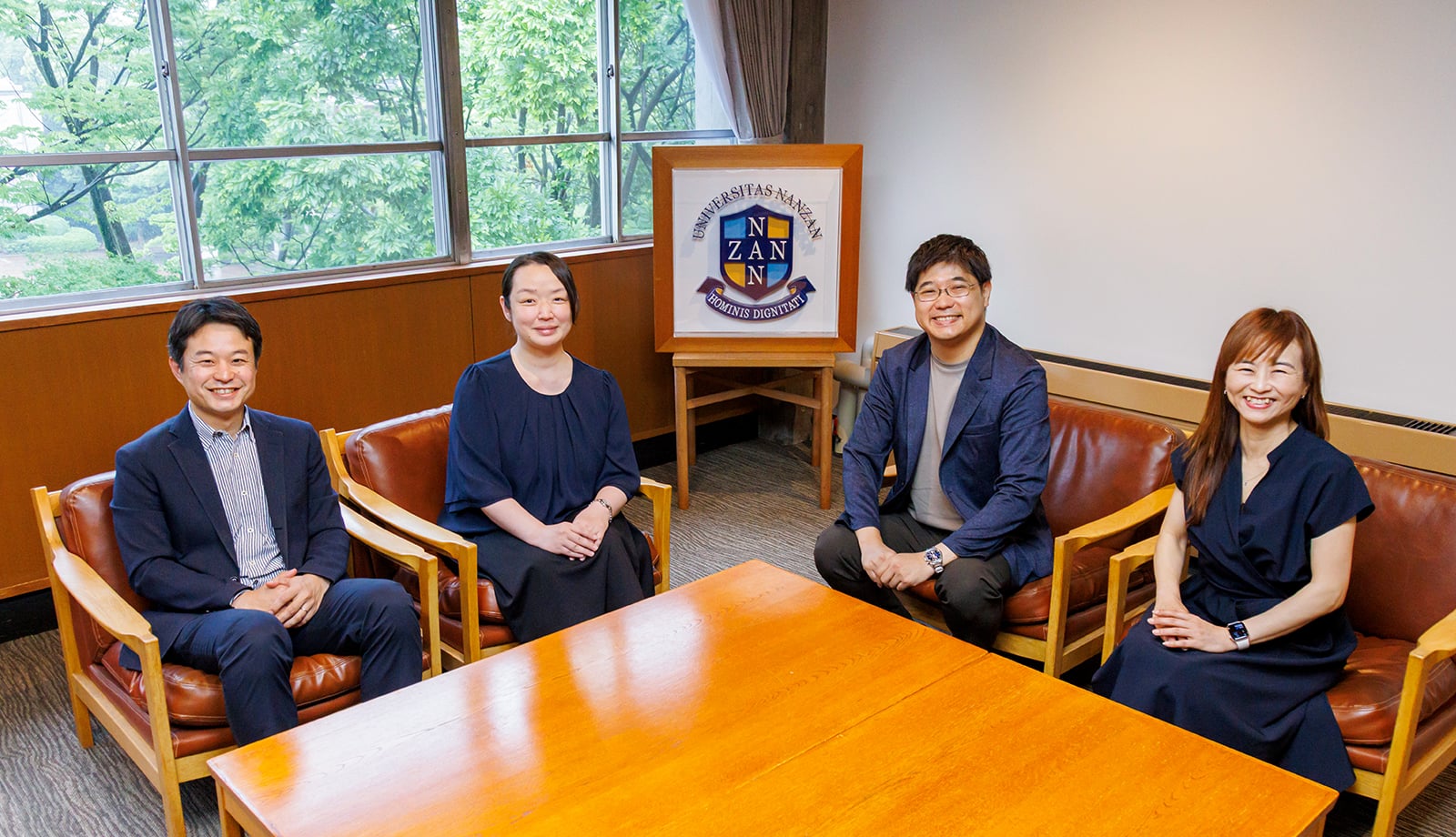
左から小市さん、森山さん、余合さん、(聞き手)同窓生 村田さん
研究と教育の両輪で。それが南山アカデミア
南山大学100周年に向けて「未来へつなぐ」座談会企画の第2弾は、教員の方々を迎えて進めていきます。研究者であり教育者、また南山メンバーの一員としての側面など、皆さんの多彩な引き出しを開けていきながら、‘一期一会’な化学反応も楽しんでいけたらと思います。まずは自己紹介、余合先生からお願いします。
余合
経営学部経営学科の余合です。南山大学に着任したのは2022年、それまで国公立の大学で過ごしてきたので、初めて来たときは緑豊かでオレンジ色が映えるキャンパスにカルチャーショックを受けました。メインストリートを中心に統一感のあるデザイン、しかも「芝生がある!」みたいな(笑)。また、20年以上前に私が関西で過ごしていた学生時代の話ですが、当時所属していたゼミと南山の南川ゼミとで合同ゼミをやったことを思い出して、「人生つながっているな」と縁を感じました。

「キャンパスという空間」の第一印象にインパクトがあったのですね。研究領域についてもお聞かせいただけますか。
余合
経営学で「人的資源管理論」という分野を専攻しています。企業における人事、「人の管理をどうするか」ということを考える学問です。「働き方改革」「女性活躍推進」「ワークライフバランス」などのキーワードには、皆さんも馴染みがあるのではないでしょうか。
これらの推進には、職業観、ジェンダー、日本企業固有の習慣など、さまざまな要因が絡み合います。経営学では一般的に「男性社会で女性管理職比率をどうやって上げるか」という視点で研究されることが多いのですが、私は例えば99.9%が女性である「歯科衛生士のキャリアを調べる」という研究から、別の視点を提示することもあります。
そのお話、気になります。後ほど改めて聞かせてください。続いて森山先生、自己紹介をお願いします。
森山
南山への着任は2015年の10月で、そろそろ10年になります。私は社会倫理研究所の第一種研究所員で、総合政策学部に所属しています。もともと専門は政治学で、国家公務員として内閣府に勤めたりしながら、自殺対策の研究、自殺予防や自死遺族支援を中心に研究活動を続けてきました。私は「‘いま動いている政治’にどう向き合うのか」ということに関心があります。自殺対策にしても、「自殺を考えざるをえなくなってしまうような社会を、どうすれば変えることができるのか」というようなテーマで研究ができる研究所は他にありません。「政治の一部に関わりながら、研究して教育ができる場所」というのは、南山が唯一無二の環境です。お声がけいただいて今は国の政策決定に関わる委員を務めているのですが、‘いま動いている政治’に携わりながら、その経験を研究に生かしつつ、大学の授業を通じて未来を担う学生への教育ができる、というとてもありがたい環境に身を置いています。

森山先生の授業は毎回、受講希望者多数で抽選になる、と聞きました。
森山
「人権をめぐって」という授業で、自殺予防や人権などをテーマにしています。これまで学生たちも、興味関心はあるけど学ぶ場がなかった、ということなんだと思います。コロナ禍のオンライン授業のときは、zoomでの受講上限999人を超えてしまったこともあります。現在は教室に入れる人数に限りがありますが、通期で2500人ほどに授業を行ってきました。
大人数の授業は大変ではないですか?人数を絞る、というお考えはなかったのでしょうか?
森山
その発想はありませんでした。授業も私にとっては教育とともに研究活動の一環で、大切な場のひとつです。自殺の問題って、一般的にはなんとなく腫れ物に触るようなイメージがあるけれど、「ちゃんと知りたい」という学生さんがいる限り、私はそれに応えたいと思っています。表立ってなかなか語られないことについても、政策を含めて実践現場に関わる機会が多い自分だからこそ、伝えられる現実もあると思っています。多感な学生時代にそういった現状に触れてもらうことで、将来、世の中を変えていくきっかけや原動力になるかもしれない。だから私はなるべく多くの学生に聴いて欲しい。年間2500人×4年間で、ほぼ南山の学生すべてに伝わるんじゃないかな、と思っています。何十年後でもいい、ふとした時に私の授業で学んだことを思い出してくれたらいい、と思っています。経営学がご専門の余合先生のお立場からしたら怒られてしまうかもしれませんが、授業では「退職の仕方」についても教えています。

余合
私はどちらかというと「退職したいと思わないように社員を引き留める視点」の研究をしていたりしますね。
森山
私が伝えたいのは、「しんどくなった時には、いのちを失う前に辞めよう」というメッセージです。たとえば、過労自殺で亡くなる方は、就職して半年とか1年で亡くなる場合もあるため、「3年がんばろう」と言って、引き留められる前に辞めた方がいい場合もあります。いったん休職をするとか、そういうことも授業のなかで織り込んだりしています。3年待たずに辞めようなんて言ったら、これはキャリア支援課にも怒られてしまいそうですが。
森山先生の授業を受けた学生が、20年後には国の中枢を担う世代になりますよね。セーフティネットの大切さを識り、実践できる若者が増えていくのは心強いと思いました。未来のタネを「育てる」、先生の意思を伺って胸が震えました。続いて小市先生、お願いします。
小市
理工学部データサイエンス学科の小市です。2008年、博士号取得後すぐに南山に着任していますから、瀬戸キャンパスからスタートしてかれこれ17年になります。研究領域はオペレーションズ・リサーチです。例えば施設を新たに作る際に、どこに配置すると一番効率が良いか、経営者の立場から言うと「一番収益が上がるか」、そういうことを研究する学問です。その際に計算が必要になってくるので、その計算を助けたり、実際に計算をしたりしています。
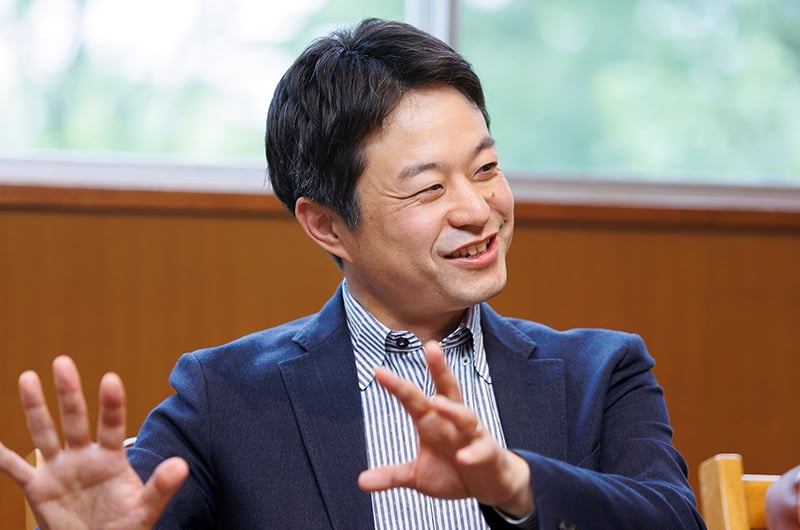
小市先生の研究業績を拝見すると、南山生に身近な話題では「図書館の書庫が本でいっぱいになりそうなんだけど今後どうしたらいいか」であったり、飛行機の効率的な運航から創薬・化学の世界まで多岐にわたります。オペレーションズ・リサーチは政府、交通、物流、ビジネスの現場など幅広い分野で活用されていて、情報社会において「なくてはならない」イメージです。
小市
社会のさまざまな課題に対して、オペレーションズ・リサーチの人間は、それを「数値で捉えて、数式にして計算して答えを出してみよう」とアプローチします。
数値に置き換えられれば何でも計算できる、ということですか?
小市
うーん、、、究極的にはそうかもしれないし、なんて言ったらいいかな。そこには「選ぶ選ばない問題」が内包されていて。突き詰めていくと「最適化」、これだとざっくりしすぎかな。人間の視点が入って初めて「最適化」という概念が意味を持ってくるのですが。
ありがとうございます、素人発想な質問で失礼しました。後ほどもう少し小市先生の研究についてお伺いしてみたいと思います。皆さん、個性豊かな自己紹介をありがとうございました。それぞれ専門領域は違いますが、現実社会では重なり合う部分がありそうです。そこはスピンオフ企画の「研究クロストーク」へ譲るとして、本題に入っていきましょう。
YAMAZATO60プロジェクト、見てました?
昨年度のYAMAZATO60について、忌憚のないご意見をお願いします。余合先生から。
余合
ポスターがエレベーター内に貼ってありますよね。私は研究室のあるJ棟8階までエレベーターで上がる間、毎日ポスターを眺めていました。その先の記事については、今回座談会に参加することになって、改めてじっくり読んだのですが、もっと発信しないともったいないコンテンツだ、と思いました。経営的な話をすると、大学のブランディングに必要な取り組みだと思います。
専門家からのありがたいアドバイスです。森山先生はいかがですか?
森山
私もポスターを見て、先生方の意外な一面を見られる機会というか、とても面白いと思う一方で、ふと「もし写真が嫌いな先生だったら、どうするんだろう」という疑問が湧いてきました。もしかしたら病気で写真に写りたくない方もいらっしゃるかもしれないし、人前に出たくない方がいるかもしれない。それでも広報したい場合は、どうすれば成り立つんだろう。今回は人物写真ありきでデザインされたポスターでしたが、言葉だけで訴求してインパクトを出すには、いろんな工夫が必要だろうな、なんてことを考えました。
なるほど、森山先生らしいご指摘ですね。デジタル世界のアバターの発想もありかもしれません。
森山
YAMAZATO60のコンテンツページはこれだけ充実した内容なのだから、学生さん含めもっと多くの方に見てもらえるといいのに、とも思いました。
多くの方にコンテンツページへ来訪してもらう導線づくりが必要ですね。森山先生が授業でお知らせしてくださったら、2500名の学生にリーチできるのでは、なんて妄想してしまいました。またご相談させてください(笑)。では小市先生、お願いします。
小市
正直あまり中まで見ていなかったのですが、、、デザイン的に統一感があって、定期的に更新されてコンテンツがどんどん増えていく取り組みだな、と眺めていました。でもインタビュー企画でそれぞれの方が「南山のどこが好きか」を語っているのを読んで、自分自身を振り返るところもあったので、そういう意味でとても面白かったです。同時に、もっと多くの学生さんにも「自分の中で南山のどこが好きか」を考えながら読んでもらえるといいな、と思いました。

Beautiful Campus&Nanzan Mindへの想い
本企画共通のテーマ、まずは「あなたにとってのBeautiful Campus」についてお尋ねします。お気に入りの場所、思い出の場所、キャンパスの魅力などお聞かせいただけますか。
小市
R棟から見える夕陽の景色です。渡り廊下からの景色も綺麗ですし、階段を降りていくところに窓があるんですけど、ちょうどいい感じで夕陽が額縁のように切り取られる時間帯があるんですよ。あとはS棟7階からバンテリンドーム方面を望む風景ですね。


先ほどまで「すべての事象を数値に置き換える」みたいな話をされていた小市先生から、こんなロマンティックなお話がでてきました。このギャップも素敵です。では森山先生、いかがでしょうか。
森山
私は人類学博物館が好きです。土器など展示物に触れることができる博物館ってなかなかないですよね。昭和初期のコーナーも好きで、童心に返れるというか、私の幼少期に使われていたものも置いてあって、とても愛着を感じます。
余合
普段は駐車場からJ棟、そして授業の教室までの往復なので、あまり情緒的な話ではないのですが、、、J棟の研究室の廊下にある窓から、東山タワーを望む景色を仕事終わりに眺めて、「明日は傘が要るかな?」などと天候確認をするように、キャンパスは私にとって日々のルーティンの一部になっている感覚があります。春休みや夏休み、また早朝の誰もいない静かなメインストリートを歩くのは楽しみだったりします。

J棟から東山タワー方面を望む風景
では次の質問、「あなたはどんなところにNanzan Mindを感じますか?」。Nanzan Mindに明確な定義はありませんので、それぞれの捉え方をしていただければと思います。
余合
南山は優秀な先生方が多いので、いちメンバーとして「私も頑張らなきゃ」と、いい意味で緊張感があります。そこが私にとって居心地のいい南山らしさかな、と思います。また森山先生が所属されている社会倫理研究所など人文社会科学系の研究が盛んなことも、私が着任した当初、とても新鮮に映ったことを記憶しています。一時期「経営管理論」という授業を受け持っていたのですが、先達を遡ると日本の経営学者の第一人者である野中郁次郎先生もかつて南山で教鞭をとっていたり、私の研究分野の学会長や、私のかつての指導教員の先生も南山に所縁のある方々だったりと、経営の研究をするうえでいい基盤になっている場所だと思います。

研究環境についても、南山はリベラルだというイメージがあります。研究者として居心地が良いんですね。森山先生はいかがですか?
森山
着任したばかりの頃、南山はカトリックの大学なので「ここで自殺の研究をしても大丈夫なのかな」と心配で、同僚の神父さんに相談しました。すると、「学問は学問、教育を否定するものではない。」というお言葉をいただいて、私は安心して研究と授業ができるようになりました。研究分野に関してもある意味で寛容というか、認め合う文化があると思います。私の研究領域ですと他大学ではなかなか得難い研究環境が、南山にはあります。

他大学だとどのような制約がかかるのでしょうか?
森山
そもそも自殺という言葉を出して欲しくない、と言われるところもまだ多いようです。
呼び水になる、というようなことでしょうか?
森山
そこが大きい誤解としてあります。本当は正しい知識を知ることが重要なのですが、「自殺予防学」の授業を開講できる大学はそれほど多くなくて、あるとすれば医学系の大学にとどまっています。ですから、全学部の学生に向けての発信ができている大学は、南山以外に私は聞いたことがありません。学生自身も「知りたい」と授業を聞きに来てくれます。大事なことは大事なこととして認めてくれる土壌があるんだな、とずっと思ってきました。懐が深いと感じます。最初は私が勝手にビビっていたんですけど、そうじゃないんだ、という発見がありました。それこそ神父職を持っていらっしゃる先生方とも普通にディスカッションができますし、教授や准教授など立場に関係なくフラットに議論ができるところが、南山の強みだと思います。
余合
少し口を挟んでいいですか?フラット、という意味では私も南山に来て「学部間の垣根がない」ことに驚きました。前任校までは縦割りの組織で、ほぼすべてが学部間で完結していましたから。
森山
上下関係など気にすることなく、研究に関してフラットに自由に発言できる環境だと思います。もうひとつ南山らしい特徴を挙げるなら、職員の方々が親身に関わってくださることも加えたいと思います。いつもありがたく思っています。
職員の方々への感謝の言葉は、これまでもよく耳にしてきました。さて、小市先生にもお伺いしたいと思います。どんなところに南山マインドを感じますか?
小市
南山は教育と研究、どちらも大切にしていますが、それが成り立つのは素直な学生が多いからなのかな、と思ったりします。学生を見ていると、我々教員も「もっといい教育を心がけよう」とモチベーションが湧いたりするので、切磋琢磨というか、向上する気持ちを「お互い持ち寄れる環境がある」と思います。

例えばどんな学生さんでしょう?
小市
私が授業で触れていない内容についても、興味を持ったことを自分で調べて質問してくる学生がいます。卒業研究の相談に乗っていると、一見脱線しているように見えることでも見方によっては「その方向性もアリだよね」と思えるようなアイデアを出してくる学生もいて、おもしろいなと思います。
「素直」といっても、受け身ではないということですね。
小市
興味を持ったことについては突き詰めていく探究マインドを持っていると思います。そんな彼らを見ていると、その才能を伸ばしてあげたいな、という気持ちになります。
先生方同士でも研究者としてはお互いライバルだし、学生との関係においてもお互いを尊重してより良い探究をしていく雰囲気が醸成されている、という感じですね。
小市
こちらの言葉が届いている、という感覚があります。知的好奇心に溢れる姿勢を持った学生が多いと感じます。
―「打てば響く感覚」、教員冥利に尽きるのかもしれませんね。伸び伸びと研究に、教育に尽力されている様子が伝わってきました。この先のトークは後編へと続きますのでお楽しみに。
後編に続く