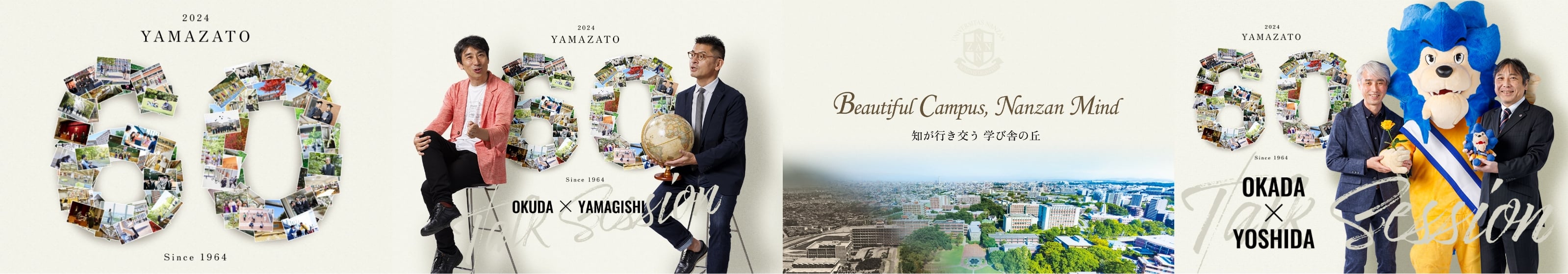多様な研究が集う交流拠点YAMAZATOキャンパス。
南山大学の研究力をわかりやすく数字で語ります。
2024年12月現在の情報となります。
南山大学の基盤は、
確かな研究力
南山大学は、「人間の尊厳のために」という教育モットーのもとに、80年近く東海圏随一の私立大学として質の高い教育を提供し、国内にとどまらず世界で活躍する卒業生を送り出し続けてきました。そうした南山大学の教育の基盤を形作ってきたのは、個々の教員=研究者たちの確かな研究力です。
南山大学は、1946年に名古屋外国語専門学校として名古屋の地にその産声を上げた時点から、アカデミズムを重視した総合大学への構想をしっかりと描き、1949年に新制大学としてスタートすると同時に人類学民族学研究所(のちの人類学研究所)を設置することで、研究拠点としての発展をはっきりと見据えてきました。

大学の発展と足並みを揃えて、カトリック総合大学としてのミッションに基づく3つの研究所が設立され、また、広く世界に目を向けた研究を学際的に進めるための4つの地域研究センター、人文社会科学から自然科学までの多様な専門知に基づき人間を深く掘り下げる研究拠点としての5つの研究センターが次々と整えられ、それぞれに充実した活動を続けてきました。そして、オープンイノベーションの可能性を秘めたライネルス中央図書館、見るだけでなく触って鑑賞できるユニバーサルミュージアムを目指す人類学博物館が、「知が行き交う 学び舎の丘」のホットスポットとして、大学内の研究者や学生はもちろん、地域の人々をはじめとする来訪者たちを日々歓待しています。
今回は、そうした多様な研究力が集う研究拠点の特徴を数字で伝えます。今も、未来も、南山大学にご期待ください。南山大学は、教育か研究かという二分法に陥ることなく、設立以来の理念に基づき、確かな研究力の基盤の上に質の高い教育を提供する「真の意味における大学」(パッヘ初代学長の言葉)であり続けます。
数字が語る南山の研究力
研究所
3
地域
研究センター
4
研究センター
5
関連施設
2
0
14の研究機関
南山大学には、3つの研究所、4つの地域研究センター、5つの個性豊かな研究センター、2つの研究関連施設があり、年間を通じて一般市民にも開かれた多様な学術イベントを開催しています。

0
刊行部数
7,209部/1年
南山大学の研究所・研究センター、大学内学会が刊行している定期刊行物の2023年度合計部数は7,209部。ほぼすべてオンライン公開されていますが、紙媒体でも多くの読者に向けて発信しています。
0
0
883,857冊、17,410種類収蔵
南山大学内にある図書館・図書室には、多種多様な学術書が収蔵されていますが、それらすべてを合わせると、図書883,857冊、雑誌17,410種類(2023年度現在)。歴代教員たちによる選書によって独自の蔵書が構築されています。
0
研究テーマは344⤴
南山大学の専任教員は344名(2024年5月1日現在)。それぞれの専門領域で活躍する南山の研究者たちが取り組むテーマは少なくとも344テーマにのぼり、時にそれぞれのテーマを交叉させ領域を横断しながら、新たな発見への対話をYAMAZATOの地で重ねています。
0%
南山大学の教員の約半数(344名中152件:2023年度現在)が、日本学術振興会の科学研究費助成事業の研究課題の研究代表者を務め、堅実な事務サポートを得ながら、日々研究に勤しんでいます。

研究機関のご紹介
南山大学には、研究拠点となる14の機関が存在します。
14個の「数字」を手がかりに、学知の扉をノックして、
「知が行き交う 学び舎の丘」YAMAZATOの地へ足をお運びください。
14
-
研究所
人類学研究所
1949
1949年
人類学研究所は1949年9月1日に「人類学民族学研究所」としてその歴史をスタートさせました。これは南山大学が設立された5ヶ月後のことであり、いうなれば大学と同じ年です。日本でも最も早い時期から人類学を取り入れた大学のひとつでもあります。1954年に現在の名称になりました。
-
研究所
南山宗教文化研究所
339
339冊
南山宗教文化研究所は、東西の諸宗教、諸文化、そしてさまざまな哲学思想の間での対話を促進すべく設立され、これまでに多数の学術誌と書籍を多言語で刊行してきました。2024年時点で、学術誌が総計255冊、書籍が総計84冊、併せて339冊を世に送り出し、世界中の研究者たちの研究基盤として参照されています。
-
研究所
社会倫理研究所
3
3人
社会倫理研究所は、1980年の設立以来、45年近く活動を続けてきましたが、研究所専任の研究所員は、たった3人。しかも、全員専門分野がまったく違います。この3人で日常的に多様な会話を重ねながら、年間10を超える一般向け学術イベントや内容充実の学術的な定期刊行物を多数編集し、数々の共同研究を進めています。
-
地域研究
センターアメリカ研究センター
18,395
18,395冊
48年間の歴史を持つアメリカ研究センターは、アメリカ研究分野の地域的研究拠点として、政治、外交、経済、社会、歴史、文化、言語、文学といった人文社会科学分野を中心に文献や資料を収集してきました。アメリカ研究センターの図書室では、2024年3月31日現在で和書2,351冊、洋書16,044冊、合わせて18,395冊のアメリカ研究図書を収蔵しており、これらはアメリカを研究するすべての研究者に開かれています。
-
地域研究
センターラテンアメリカ研究センター
3
3言語
センターは、ラテンアメリカとスペインに関する記事をスペイン語、ポルトガル語、英語の3つの主要言語で掲載する学術誌「Perspectivas Latinoamericanas」を発行しています。この学術誌には、センターの研究者だけでなく、世界中の学者も寄稿しています。彼らの論文は国際的な科学水準を満たし、これまでにない世界的な広がりを見せています。
-
地域研究
センターヨーロッパ研究センター
9
9分野
ヨーロッパ研究センターに所属するセンター員の専門分野は、政治学、法学、経済学、社会学、歴史学、哲学、文学、言語学、音楽学と9分野にもなります。このような多様な分野から現代ヨーロッパの動態について理解を深めるために、講演会やイベントを開催し、ヨーロッパ研究センター報を毎年発行しています。
-
地域研究
センターアジア・太平洋研究センター
21
21世紀
アジア・太平洋研究センターは、外国語学部アジア学科と総合政策学部の新設を機に、オーストラリア研究センター(1986年設立)とアジア研究センター(2003年設立)を統合する形で2005年に活動を始めたアジア・太平洋地域の地域研究拠点です。アジア・太平洋地域では、21世紀の活力ある地域協力に向けた様々な試みが行われており、本研究センターもまた、21世紀=アジア・太平洋の世紀の研究センターとして活動を展開しています。
-
研究
センター言語学研究センター
150
150編
2003年の創設以来20年以上にわたり、毎年複数の国際ワークショップ・研究会を開催し、その成果を言語学専門誌 Nanzan Linguisticsにまとめ出版してきました。総計24巻150編以上の学術論文がこれまでに発表され、世界中の研究者に幅広く読まれ、引用されています。
-
研究
センター人間関係研究センター
9587
9587名
人間関係研究センターでは、主に社会人の方を対象とした学びの場を提供しています。その柱の一つである『公開講座』では、ラボラトリー方式の体験学習やスタッフの専門性を活かした様々な講座を通して、人と人との関わりを実践的に学ぶことができます。これまで開催された公開講座の修了者数は、2024年10月6日現在で、延べ9587名にのぼっています。
-
研究
センター経営研究センター
42
42年
経営研究センターが全学組織となったのは1985年ですが、前身である経営学部の下での経営研究センターは1983年に、さらにさかのぼって遅くとも1982年にはワークショップを開催・ワーキングペーパーを発行しています。以後一貫して、学内外の研究者に経営研究の機会と支援を提供して参りました。
-
研究
センター理工学研究センター
250,677,547
250,677,547円
理工学研究センターは、理工学部・理工学研究科と社会の連携の推進と、それによる学部・研究科の教育研究の活性化を目的として、2005年に設立されました。2005年の設立以来、受け入れた研究費は250,677,547円。理工学部・理工学研究科の研究者による研究シーズ集をオンラインで公開しています。
-
研究
センター法曹実務教育研究センター
2006
2006年
大学院法務研究科に付属する法曹実務教育研究センターは、南山大学経済学部在学中に医療事故に遭われ、22年に及ぶ長期療養の後に生涯を閉じられた故稲垣克彦氏のご両親からの寄付に基づき、医療過誤被害者の相談、救済、医療事故裁判に通暁した法曹人育成を目的として設立されました。寄付のお申し出があったのが2006年。その翌年の設立以来、活動を続けています。
-
関連施設
南山大学人類学博物館
700,000
700,000年
人類学博物館は、多数の学術資料を所蔵し、教育・研究資源として活用しています。さらに、そうした学術資料について、障がいの有無や年齢、文化的差異を超えて、誰もが学べるよう、ほとんどの資料を手に取って見ることができるようにしました。700,000という数字は当館で最も古い石器の年代で、これも手に取って見ることができます。南山大学人類学博物館は、誰もが楽しめる「ユニバーサル・ミュージアム」を目指す博物館です。
-
関連施設
南山大学ライネルス中央図書館
8298
8298種
「カトリック大学の図書館として相応しいキリスト教関係資料群を構築することにより、近代日本におけるキリスト教史を研究する国の内外の研究者に資すること」を目的として開設された南山大学カトリック文庫は、主に明治・大正・昭和初期に成立した聖書、祈祷書、聖歌集、要理書およびそれらの解説書、聖人伝、布教資料、教会・修道会史資料などのキリスト教関係資料(刊行物以外を含む)を所蔵しており、その数は8,298種(2024年9月末現在)です。
※2024年12月現在の情報となります。
多様な研究力が集う
交流拠点
南山大学が1964年に山里町に移転してから60周年を迎えました。
このキャンパスは建築家アントニン・レーモンドが「自然を基本として」をコンセプトに、マスタープランから設計までを手掛けたモダニズム建築の傑作の一つです。このコンセプトを継承しつつ増築、改修等を行い、キャンパスを保存活用してきた本学の取り組みがこのたび日本建築学会賞(業績)を受賞しました。
これを機に「山里キャンパス」60周年を記念した様々な企画を開催しています。
「山里キャンパス」60周年記念
南山生が制作した「南山大学PR動画」
南山大学は積極的に研究力を発信していきます。
南山大学 公式サイト