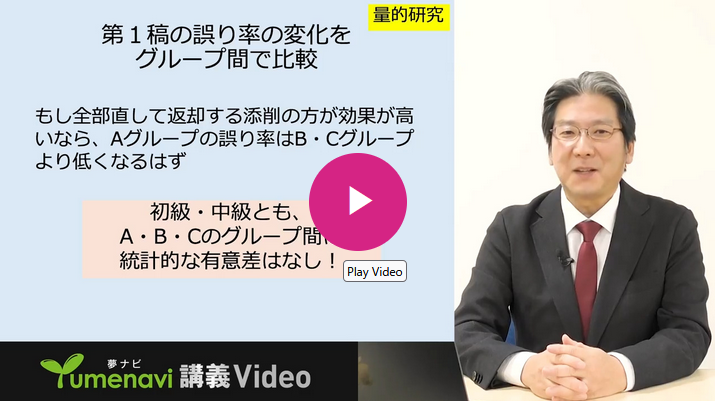学部別インデックス
外国語学部・ドイツ学科
太田 達也
| 職名 | 教授 |
|---|---|
| 専攻分野 | ドイツ語教育研究,外国語教育学,応用言語学 |
| 主要著書・論文 | Die Wirkung von Fehlerkorrektur auf Überarbeitungsprozesse und -produkte beim fremdsprachlichen Schreiben. Eine empirische Studie unter japanischen Deutschlernenden. (単著) München: Iudicium. 『NHK CDブック ラジオドイツ語講座 からだで覚える実践ドイツ語』(共著,NHK出版) 『ドイツ語おもしろ翻訳教室』(単著,NHK出版) 『ニューエクスプレスプラス ドイツ語』(単著,白水社) Wörterbuchbenutzung und Aktivierung des grammatischen Wissens - eine empirische Studie mit japanischen Deutschlernenden. (単著) In: M. Hoshii / G. C. Kimura / T. Ohta / M. Raindl (Hrsg.) (2010): Grammatik lehren und lernen im Deutschunterricht in Japan - empirische Zugänge. München: Iudicium, pp. 88-102. Was denkt der Lerner, was sieht der Lehrer? - Schreib- und Korrekturprozess von Deutschlernenden und -lehrenden. (単著) In: C. Fandrych / I. Thonhauser (Hrsg.) (2009): Fertigkeiten - integriert oder separiert? Zur Neubewertung der Fertigkeiten und Kompetenzen im Fremdsprachenunterricht. Wien: Praesens Verlag, pp. 107-124. |
| 将来的研究分野 | 日本におけるドイツ語教員養成の現状把握と改善に向けての提言 タスク・行動中心型の外国語授業におけるインターアクション 日本語を母語とするドイツ語学習者に対する明示的指導およびフィードバックの効果 |
| 担当の授業科目 | ドイツ語,上級ドイツ語作文,ドイツ語通訳法,ドイツ語科教育法,基礎演習,ドイツ語実践演習,演習 |
複数の言語を学ぶ意義
みなさんはすでに英語を学び、そしてほとんどの人は日本語を母語として流暢に話すことができるでしょう。では日本語と英語の2つの言語さえ習得すれば、世界の大方のことは把握できると考えてよいでしょうか。
ここでひとつ、実際にあったエピソードをお話しましょう。私がドイツに留学していたときのことです。下宿先の年配の女性に、「あなたはスポーツをされますか?」と尋ねられました。当時、私は流鏑馬(やぶさめ)という弓馬術をやっていましたので、「はい、弓と馬を。」と答えたところ、その女性は真顔で私に、「あなたのお父さんはサムライですか?」と尋ねたのです。これには驚きました。
同じ頃、世界中にあるハンバーガーショップのドイツ支店では「日本フェア」のようなものが開催されていて、トレイに敷かれたペーパーには「サムライバーガーの食べ方」が印刷してあったのですが、その「サムライ」の絵はどうみても日本以外の東南アジアの格好をした人物で、私の目にもエキゾチックに映ったものでした。
これと似たようなステレオタイプ的な言動は、あちこちでよくみられます。「ドイツ」と聞くと「ビール」や「ソーセージ」といったイメージを思い浮かべる人は少なくないでしょう。しかしそれは、先ほどの「お父さんはサムライですか?」とさして変わりないのです。「日本」と聞いて「寿司」を思い浮かべる外国人は少なくありません。しかし現実の日本人の多くは、寿司をそんなにしょっちゅう食べてはいないのではないでしょうか。同じように、ドイツ人ひとりひとりと話してみると、Hans君は「ビールよりもワインが好き」と言い、Annaさんは「肉は苦手、ベジタリアン」といった具合で、ひとくくりには「ドイツ人はこうだ」とは言えないものだとわかります。ドイツの人々をよりよく知るには、本やインターネットでの情報収集だけではなかなか本当の姿が見えてきません。やはり直接、交流することが一番です。
ではその交流の際に、いったい何語を使うとよいか。英語は一見便利そうですが、しかし相手にとっても外国語です。ドイツ語であれば、ドイツの大多数の人にとって母語または生活言語です。ドイツの農家の生活について調べたいなら、現地に行って直接話を聞くのがよいでしょうし、文献調査であればドイツ語の資料にあたる方が、日本語や英語で書かれた資料に頼るよりもよいのは言うまでもありません。もし東海地方のお祭りを研究しようという人がいたとして、その人が日本語をまったく理解できなかったとしたら、調査から見えてくるものに限りがあるのは想像に難くありませんね。
さて、冒頭の問いに戻りましょう。日本語と英語の2つの言語さえ習得すれば、世界のだいたいのことがわかると考えてよいのか。答えは明白でしょう。世界中に住む人々のうち、英語を話す人々は全体の2割弱と言われています。「英語を話す人々」には、英語の母語話者だけでなく、第二言語として話す人々も含まれます。ということは、世界の約5分の4の人々は、英語を話さない人ということになります。英語でカバーできる範囲は、じつはごく一部なのです。
日本は英語が苦手な人が多いことで知られていますが、モノリンガル(1つの言語しか話さない人)は、世界の中ではむしろ少数派です。多くの人は2つ以上の言語を話します。多言語を話す人(マルチリンガル)は、世界を見る「窓」を複数持っているため、異文化に対する感受性が高く、複眼的で広い視野を持つ人が多いと言われています。あなたも大学で日本語・英語以外のもう1つの言語を身につけ、世界をより多角的に見る視点をもったマルチリンガルになりませんか?